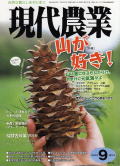
| ■ |
|
|
|
|
現代農業 2010年9月号 |
| home | おはら野の四季 | おはら野 農園 | 野良日記 | 遊びたい | おはら野ママ | link |
おはら野 農園へようこそ
農文協、「農山漁村文化協会」
いまこの団体の成立の過程を知っている人は少ないだろう、
百姓から農業に変わっていく戦後日本の鬼子なのかも知れない
一部の農学者は、近代農業に貢献した。一部の農学者は百姓にこだわった。
近代と農業を4文字熟語にするには、近代の意味を問わねばならない。農業という産業分類は近代が産んだものだ。
その近代と農業の蜜月は、公害・環境破壊と言うagricultureに包摂される実に文明論を巻き込んで進行した。
いま問い直されているのは、この文明論だと思う。
私は農本主義者に組しない。その程度の節度は持ち合わせている。
数多くの宗教者が農法の名で農業に参加している。きわめて自然な所為だとは思う。
思うが、近代の意味を性急に断じて未来を語ることはないと、農本主義者・宗教者に言うべきだろう。
科学信奉する一部の農学者と追随者の、科学する行為は、
宗教する行為(神学)からの離脱を、哲学する行為と考えたのが近代哲学の始まりだった、とするならば
その近代が見直されている現代にあっては、「科学信奉」と呼び捨てにされて仕方なかろうと、言いたい。
現代は、いつの時代にも現代が存在していた、その現代である以上の意味は持ち合わせていない。
それであるが故に、農文協が「現代の農業」に言及する意義は大きい。
現在を過去から解放すること われわれはじぶんたちの生きている現在と完全に同時代にいることはない。
歴史は仮面をつけて進行する。 『革命の中の革命 La révolution dans la révolution ? 』レジス・ドブレ
理論から導き出される実践はときとして過ちをおかす、実践に裏打ちされた理論は当初理論家から排撃を受ける。
| -大幅に改造中です。-09 July, 2010 | |
| 私にとって「現代農業」は文字通り雑誌。 理論誌ではないので、多くの農家の、関係者の実践の記録がてんこ盛り。 どう読むか、何を汲みとるのか、興味・関心・注目した記事を時系列で振り返るのにindexが欲しい。 備忘録かもしれない。 雑誌「現代農業」公式サイト 目次・内容が閲覧できます。→http://www.ruralnet.or.jp/gn/ |
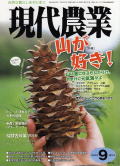 |
|
|||||||||||
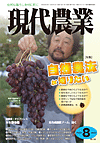 |
|
アンダーラインのリンクはhttp://www.ruralnet.or.jp/gn/内の各ファイルに行きます。戻ってくるには、ブラウザでお願いします。 |
||||||||||
| ああだ、こうだと書きます。 ・記事をお読みになっている方のみに書いています。記事の引用は特にしません。 ・著作権や商標など諸権利に配慮していますが、お気づきの点がありましたらご連絡お願いします。 |
| 未整理のまま以下は残っています。 雑誌「現代農業」公式サイト 目次・内容が閲覧できます。→http://www.ruralnet.or.jp/gn/ |
|
2010.01 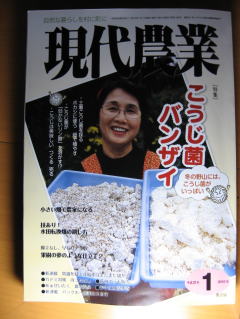 |
特集 こうじ菌バンザイ酵母菌とこうじ菌、今一つ理解できない。それで、 青木恒男:①常識を疑えば稲作はまだまだ儲かる p118 |
| 2009年 以前 | |
2009.12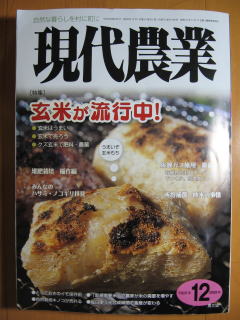 |
|
2009.11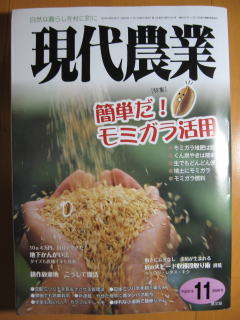 |
|
2009.10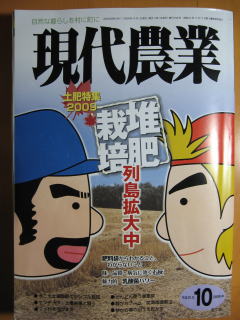 |
炭素循環農法、たんじゅん農法2004年10月号(初出) ブラジルより-糸状菌を生かして野菜づくり「炭素循環法」の実際- |
2009.9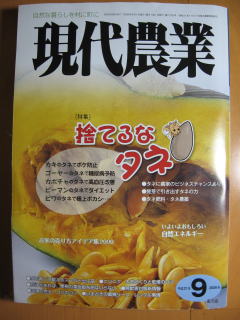 |
|
2009.8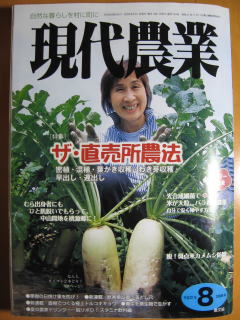 |
|
2009.7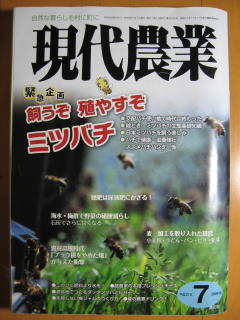 |
|
2009.6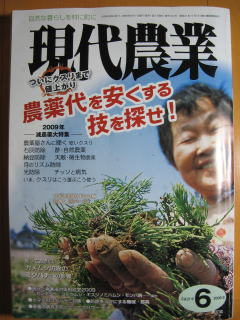 |
|
2009.5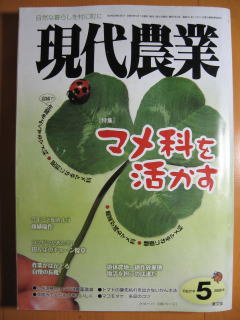 |
|
2009.4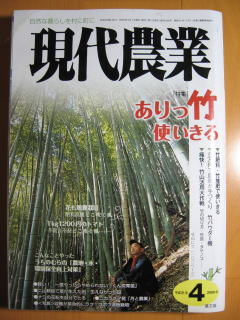 |
|
2009.3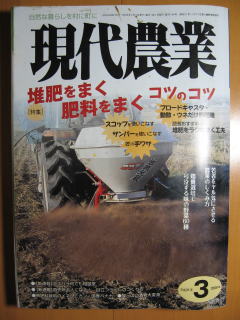 |
特集:堆肥をまく 肥料をまく コツのコツ 滋賀・西老蘇:生産原価「1表一万円」の米づくりに挑戦 桐島正一・四万十:鶏糞栽培で、号泣する味の野菜60種 |
2009.2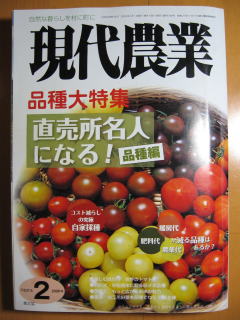 |
特集:品種大特集 直売所名人になる 品種編青木恒男:品種力を駆使 定番野菜でも人が出さない時期にずらし売り p54 ホルンスナックの9月播き 桐島正一・四万十:タネ代1/3で市販を超えるタネの採り方 p181 吉村俊弘:①アスパラ何でも相談室 立茎のポイントを教えてください p172 渡辺臣・沖縄:無肥料無農薬の国産バナナつくり p220 |
2009.1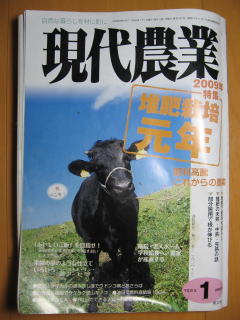 |
特集:堆肥栽培元年
小川光・福島:溝だけ落ち葉堆肥 p112 青木恒男:ストックは儲かる5 スプレーストック摘芯術 |
| 雑誌「現代農業」から、スリリングな記事をピックアップした | |
モミガラ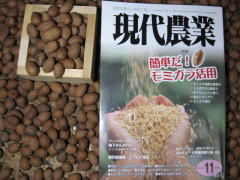 2009.11月号 |
特集・簡単だ!モミガラ活用モミガラは単純な農法に適していると思う。 |
炭素循環農法、たんじゅん農法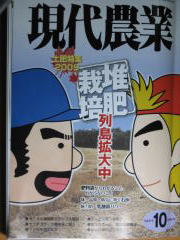 2009.10月号 雑誌「現代農業」から、記事を引き出した。 読んでいて読んでいないものだ。よくあることだが改めて思い知った。 目次を書き出した。それ以上ではない。編集業務をすれば判ることだが、普通、タイトルや小見出しは編集者が著者と相談して考え決める。 本文をお読みください。 |
2004年10月号(初出) ブラジルより-糸状菌を生かして野菜づくり「炭素循環法」の実際- 畑に必要なのは肥料より「炭素」 林 幸美 P112 (記事の www.stkm.net/tenuki/はhttp://page.freett.com/tenuki/etc/home.htmlに移行 たつ) 2009年10月号 静かなブーム 炭素循環法 城 雄二 P282 2009年10月号 ピーマンで炭素循環法三年目、畑が変わり始めた(茨城・遠藤弘さん) 編集部 P288 2009年10月号主張 堆肥栽培は、地域にも、地球にも効く 農文教論説委員会 P40 (紹介 p44 2008年10月号 「炭素循環法」を実践 廃菌床と草だけでアスパラ二町栽培 八重沢 良成 P238 「ふうちゃん農場」www.fuuchan-nouen.com 2005年 9月号 廃菌床は、最高の高炭素有機物 林 幸美(まとめ編集部) P75 リンクについて。2009.9.16現在、有効であることを確認しているがその後の変更はフォローしていない。 |
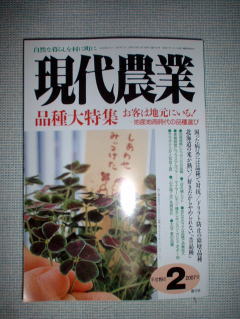 |
07年02月号 品種大特集 |
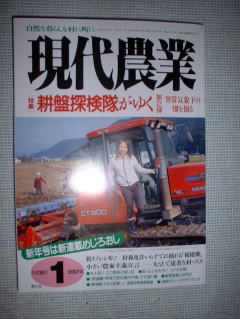 |
07年01月号 耕盤。いろんな角度から考えることができる。熱帯雨林、マングローブの板根。単植林の日本の杉林。いずれも腐葉土の層が薄く、保水力も保肥力もない。 この号で取り上げているのは、作土、作物を作っている土の中はどうなっているのか調べている。 つまり人が作った地面の中を探検している。 |
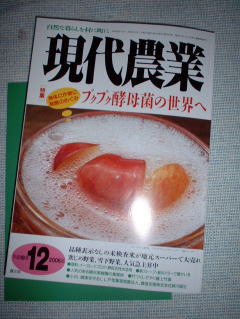 |
06年12月号 ブクブク発酵菌の世界へ 発酵、土作りのすべて。 繰り返し特集記事になっている。 |