おはら野の四季/ 春/ 夏/ 秋/ 冬/ 虫たちの生活誌 おはら野の草花 姉川水系・用水アルバム
 |
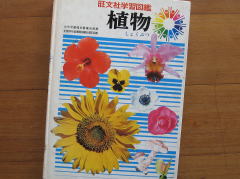 |
 |
 |
| 草花- | 植物-旺文社学習図鑑 /1976 | きのこ-畑や雑木林のきのこ | 鳥たち-花鳥風月というではないか |
おはら野の草花
| home | おはら野の四季 | おはら野 農園 | 野良日記 | 遊びたい | おはら野ママ | link |
おはら野の四季/ 春/ 夏/ 秋/ 冬/ 虫たちの生活誌 おはら野の草花 姉川水系・用水アルバム
 |
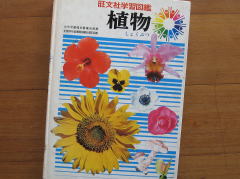 |
 |
 |
| 草花- | 植物-旺文社学習図鑑 /1976 | きのこ-畑や雑木林のきのこ | 鳥たち-花鳥風月というではないか |
タンポポ カタクリ ショウジョウバカマ カタバミ ヤシャブシ ?バッコヤナギ 金木犀 クロモ キカラスウリ
| カキドオシ /目 シソ科 カキドオシ属. | ||
|---|---|---|
 |
16 April, 2010 ぐずぐずしている季節だが、確実に進んでいた。初夏の準備をしているようだ。ハウスの中、外から侵入してきた。文字通り、垣通しだ。大概の障壁を超えて這っていく。 おおいぬのふぐりに似た青というか、薄い紫の花が咲く。この淡さがいい。 |
|
| 水仙 /目 ユリ科 属. | ||||
|---|---|---|---|---|
 |
10 April, 2010 ←今年になってから、何度か水仙をHPのあちこちに取り上げた。おはら野に咲く水仙、人が栽培していたものが、屋敷や畔・小畑に咲いている。みんな草刈りや夏草刈りなどで、養生しながら育てているような、手入れだけのような状態だ。 おいおい書いていきたい。米の減反政策がはじまったとき、転作田で商品作物、野菜などの栽培が奨励された。この地方ではその一つとして、水仙の球根栽培がはじまった。球根を育てて、売るのである。見事な失敗をした。 水仙に限らず、すべて失敗したと言ってよい。管轄のJAレーク伊吹の営農部隊は、米作りを指導する人がいるだけで、それも県の指導の下請けと実行部隊と言っていい。彼らの努力と日常はその程度にしか支持されていない不幸がある。 そんなこととは別に、ばあさまとじい様がJAと一緒にやってきたもろもろの形見だと思って水仙を眺めている。すべてを否定するのではなく、すべてを隠ぺいさせずに、ありのままを今にこうして水仙は伝えている。 |
|||
| カタクリ / ユリ科 カタクリ属. | ||
|---|---|---|
 |
06 April, 2010 カタクリ:ユリ科カタクリ属 おはら野の雑木林にはない。今や希少の花となったが、希少にしたのは野草愛好家や、花大好き人間が群生地から持ち出したから。 雑木林の木漏れ日が当たり、人が芝刈りに出かけて、地面がさほど乾燥しない土地に群生していた。 3~4月に地上部が現れ初夏には地下の鱗茎のみになる。つまり人が野山に下草刈りに出かける頃、芝刈りに出かける頃は地上部が無い。従って山寺や神社のさほど下草の無い境内なんかが絶好の生息地になり、また保全もされた。 人とともにあったカタクリも、人でなしの人に、咲いた花が奇麗だからと持ち帰ってしまったから共生出来なくなった。 |
|
 |
彼岸花と同じように、人が住む所に、咲いていた花であって、人のいないところには群生できない。それほど、かつては人は山に入り、山から芝や、草を得ていた。 「人里離れた、山里」と、山棲みの人たちの集落を呼んだ時代はすでになく、「里山」なる軟弱な里芋言葉がまかり通っている。今人が住む人里と、山棲みが住む山里と、流行りと移ろいの区別ができず、流行り即進歩などと思う今里の人たちにいつまでも時代を任せる訳にもいかんだろう。 「里山」語を否定せよ、しっかり山里を守れ、、、、 |
|
14 April, 2010 おはら野の雑木林にカタクリは生えていないので、少し遠出した。 おはら野の雑木林にカタクリは生えていないので、少し遠出した。 花が咲いている時期、大勢の人が押し寄せると根こそぎ無くなる。他で育たないのが判っていても持ちかえる。困ったもんだ。
  ←ショウジョウバカマ。カタクリと一緒に咲いていた。おはら野より濃い花色だった。 ←ショウジョウバカマ。カタクリと一緒に咲いていた。おはら野より濃い花色だった。 日当たりと、木漏れ日、花は陰った日には開かない。   |
| ショウジョウバカマ /ユリ科ショウジョウバカマ属:猩々袴 | ||
|---|---|---|
 |
28 March, 2010 ショウジョウバカマ おはら野の雑木林 猩々袴、優雅な名前がカタカナだと中々伝わらない。 猩々:猩猩(しょうじょう、猩々)は、中国に由来する伝説上の動物である。またそれを題材にした各種の芸能における演目。さらにそこから転じて、大酒家や赤いものを指すこともある。この記事の中で、能の演目及び民俗芸能についても記述する。 人語を解し、赤い顔をした人間のごとき容姿で、酒を好むとされている。元来は礼記に「鸚鵡は能く言して飛鳥を離れず。猩々は能く言して禽獣を離れず」とあるのが出典である。後代の注ではしばしばオランウータンなどの大型類人猿に擬せられる(猩々はオランウータンの漢名でもある)。 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%A9%E7%8C%A9 袴(はかま)は、和装において腰より下を覆うようにして着用する衣服の一種。着物の上から穿き、紐で結ぶ。弥生時代にその原型が成立し、近世期においては主に男子において用いられ、礼装とみなされてきた。 |
|
 |
 種を作って発芽して、という普通の繁殖もするが、落ち葉など地面に埋もれた葉の先から、発根・発芽して芽が出た頃、葉が朽ちる。 種を作って発芽して、という普通の繁殖もするが、落ち葉など地面に埋もれた葉の先から、発根・発芽して芽が出た頃、葉が朽ちる。そんな一風変わった増殖をする。群生しているショウジョウバカマを見ていると親株とおもわしい株を取り囲むように生えている。 カタクリと同じ時期に咲く。林縁の春の陽射しがまだ柔らかい頃、淡い空気の中で華やぐ。その後、春蘭の花が見られる。 ワラビ、竹の子の季節まであとひと月 |
|
| かたばみ /フウロソウ目 カタバミ科 カタバミ属. | ||||
|---|---|---|---|---|
 |
11 March, 2010 ←これを見て、カタバミだと言った人がいる。かなわん。
それで、×20で、やっぱりカタバミだったと、おっしゃる。目盛は1mm。普通は、↑を見てカタバミだと言うもんだ。 酢漿草(サクショウソウ)、絞り汁は虫さされに効くそうだ。 この湯たんぽのような欠刻でビニールのようなツルツルした表面にもくっつく。昨年、熟した実がはぜ飛んで、ビニールにこべりついた。 |
|||
| ヤシャブシ カバノキ/科 ハンノキ属. | ||||
|---|---|---|---|---|
 |
19 February, 2010昨日、長浜のジャスコで写真を撮った。実がうまく写っていなかったので持ち帰った枝を改めて撮った。このように雌花、雄花、昨年の実が同世代する。 |
|||
 |
てえと、なんだ。靴墨もタンニンかえ、口に入れたり、足に塗ったり、草木染めってのは上品な趣味だが、ほんの30年も前だったら、あんたすべてこれ、天然自然の顔料だったんだ。 また一つ賢くなった。 12 March, 2010 長浜、茶臼山古墳から南へ。カサの開いたヤシャブシの実
|
|||
 握り飯をほおばりながら、ゆったり歩いてみたい。所々に藤棚ベンチがあって過ごしやすそう。 稲木に使う夜叉五倍子は、ハンモックを架けるにはちとスパンが長い。 |
08 March, 2010 長浜市 茶臼山古墳から南へ、農道がプロムナードになっている。用水が石組になって蛇行している。春の散歩に今、期待している。 国道365から別れ(西濃運輸)馬車道に入ったすぐ左手に茶臼山古墳がある。そこから馬車道を少し離れ平行して南にあるく。プロムナードの終端を右折すると、郵便局のある交差点(馬車道)に出る。  カワウの巣→こんな農道に巣を作って カラスに似てそれほど人を嫌わないからここで営巣できるのだろう。巣籠りの季節には葉が茂って、それでいいのかもしれない。 馬車道を更に南に、北陸道・長浜ICの入り口ロータリーのケヤキにも巣を作っている。 車が多い意外な場所だけど、石を投げられたり、取り外そうにも高速株の人さまの機動性が鈍い所轄だから、いいのか。 |
|||
 |
12 March, 2010 ←ケヤキだけど、まあいいじゃない。巣が二つ。  こういうところだ。 こういうところだ。 |
|||
 |
02 April, 2010 ←ヤシャブシが発芽した。3月12日にカサが開いて種がこぼれたヤシャブシを採り播きした。なんとやくざに発芽するんだろう。そうでなければ切り開かれた林辺にイの一番に占領することはできないのだろう。 |
|||
| ばっこやなぎ跋扈柳 /科 属. | ||
|---|---|---|
 |
08 January, 2010 虫コブだろうか、三島池の木にこのようなコブが。木の名もしらない。跋扈柳にした  オブジェ。冬のリビングの飾り。 →虫たちの生活誌 in おはら野→むしこぶ |
|
| 09 March, 2010→ |  住民になってひと冬、花瓶に生けたバッコヤナギが根を伸ばしている。もう少しだ、ポカポカしてきたら庭に植える。 住民になってひと冬、花瓶に生けたバッコヤナギが根を伸ばしている。もう少しだ、ポカポカしてきたら庭に植える。 |
|
| 金木犀 /科 属. | ||
|---|---|---|
 |
26 September, 2009金木犀。10月の花、この花が匂ってくると10月なんだなあと。2009年は例年になく早く咲いた。 |
|
| クロモ トチカガミ科クロモ属. | ||
|---|---|---|
 |
04 August, 2009クロモ。カワエビの水槽に入れたクロモから出来たクロモの花。左は花粉 実体顕微鏡×20 |
 |
 |
05 August, 2009 改めて水槽のクロモを撮った。水面に浮いている。 中央の白いのが花、その下に小さく付いているのが花粉。 ブルーなのはゴミ? |
| キカラスウリ /科 属. | ||
|---|---|---|
31.7.1009 |
データ復活。キカラスウリ近くの住宅地に咲く。夜に咲いて、朝にはしぼんでいる、狙いをつけないと撮影できない。家の畑にも生えているが、株が小さくて、咲き乱れるほどではない。 小さな実をつけている。 |
|
| /科 属. | ||
|---|---|---|
 |
虫癭(ちゅうえい)この桜の葉の中に幼虫がいます。葉の中に卵を産んで冬越し。 2009年春 |
|
| /科 属. | ||
|---|---|---|
| entry form | ||
おはら野の草花へ戻る